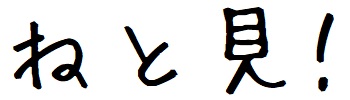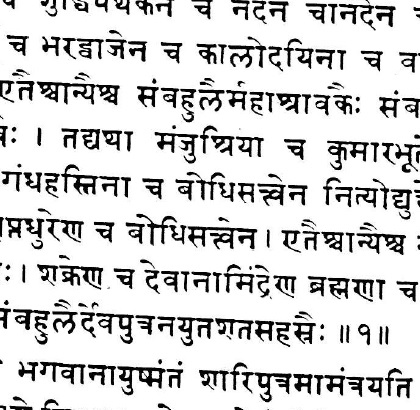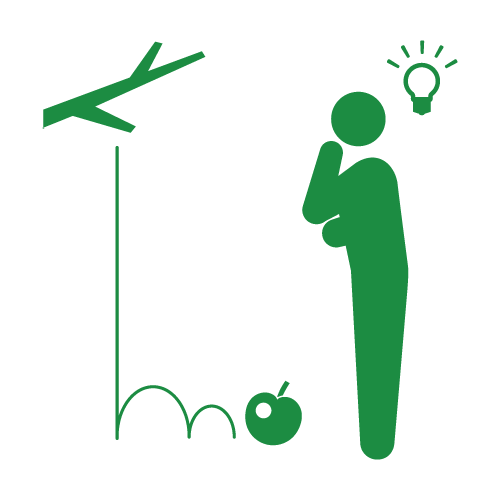夏目漱石『こころ』の散歩道
「日本で一番売れている」本(2016年時点) cf,漱石没後100年、人気衰えず 書店で文庫フェア 夏目漱石『こころ』(新潮文庫版) 夏目漱石後期三部作の一つ『こころ』。 その中でも第三章にあたる「下 先生と遺書」は今でも高校の教科書に掲載されている。 あらすじに関しては……長くなるので以下のサイトに譲ります。 cf,夏目漱石「こころ」のあらすじを紹介 さて、主人公の『私』が鎌倉で出会った『先生』は、学生時代に現在の文京区小石川にある伝通院裏で下宿していたのですが、物語のキーパーソンで ...
サンスクリット文法編6~活用Ⅲ 第2次活用・準動詞~
サンスクリット文法編~活用 目次~ 活用Ⅰ 動詞・現在組織 総説 現在組織 ・1、第1種活用 ・2、第2種活用 活用Ⅱ アオリスト・完了・未来・受動態 アオリスト組織 完了組織 未来組織 受動態 活用Ⅲ 第2次活用・準動詞 第2次活用 ・使役活用 ・意欲活用 ・強意活用 ・名詞起源動詞活用 準動詞 ・現在・未来・完了・過去分詞 ・未来受動分詞(動詞的形容詞) ・不定詞 ・絶対分詞 第2次活用 使役活用 動詞語根はすべての時制・法・態において使 ...
サンスクリット文法編5~活用Ⅱ アオリスト・完了・未来・受動態~
サンスクリット文法編~活用 目次~ 活用Ⅰ 動詞・現在組織 総説 現在組織 ・1、第1種活用 ・2、第2種活用 活用Ⅱ アオリスト・完了・未来・受動態 アオリスト組織 ・各アオリスト ・指令法、祈願法 完了組織 ・重複完了 ・複合完了 未来組織 ・単純未来 ・複合未来 ・条件法 受動態 活用Ⅲ 第2次活用・準動詞 第2次活用 ・使役活用 ・意欲活用 ・強意活用 ・名詞起源動詞活用 準動詞 ・現在・未来・完了・過去分詞 ・未来 ...
サンスクリット文法編4~活用Ⅰ 動詞・現在組織~
サンスクリット文法編4~活用Ⅰ 動詞・現在組織~ サンスクリット文法編~活用 目次~ 活用Ⅰ 動詞・現在組織 総説 現在組織 ・1、第1種活用 ・2、第2種活用 活用Ⅱ アオリスト・完了・未来・受動態 アオリスト組織 完了組織 未来組織 受動態 活用Ⅲ 第2次活用・準動詞 第2次活用 ・使役活用 ・意欲活用 ・強意活用 ・名詞起源動詞活用 準動詞 ・現在・未来・完了・過去分詞 ・未来受動分詞(動詞的形容詞) ・不定詞 ・絶対分詞 総説 動詞は ...
後鳥羽院を巡るフィールドワーク【大原御陵・水無瀬神宮・隠岐】
後鳥羽院 第二版 後鳥羽院 (コレクション日本歌人選) Field work on Go-Toba Tenno[6,Aug,1180~28,Mar,1239(14,Jul,Jisho4~22,Feb,enoh1):82nd emperor(reigning:1183~1198)and Retired Emperor]. He was also a master of Waka(Waka is Japanese traditional poetry) in Japan medieval history. ...
≪文系の人向け≫『リーマン予想』ってなに?
さて先日、数学史上屈指の難問『リーマン予想』がついに解決されたかという話題が世界中を駆け巡りました。 cf,ついにリーマン予想が証明された!? (とね日記) その後の数日間で一気に雲行きが怪しくなり、今では話題にも上がってこなくなってしまい個人的にはちょっと残念なのですが、私自身長らくその予想がどういうものかということに興味があり、今回は個人的な復習の意味も兼ねて『リーマン予想』について書いてみようと思います。 私が学生の頃(2000年代あたま)、『リーマン予想』と並んで長年解決されてこなか ...
サンスクリットについて……
デーヴァナーガリー文字やサンスクリット文法について解説をしていますが、そもそものサンスクリットについて詳しい説明(事始め1で軽く触れただけ)をしていないことに今更ながらに気付いたので、今回はそこらへんの話しをば。…… もともと文法を本格的に解説するつもりではなかったので、そこら辺のことにはすっかり意識が向いていませんでした。 ◎サンスクリットとは…… サンスクリットとはインド・アーリヤ系語族、インド・イラン語派に属する古代語の一つ。インドを中心に中東~東南アジアで用いられてきた。 原語saṃskṛ ...
サンスクリット文法編3~曲用Ⅱ 代名詞・数詞~
サンスクリット文法編~曲用 目次~ 曲用Ⅰ 名詞・形容詞・比較法 総説 名詞・形容詞の格変化 ・1、母音語幹 ・2、子音語幹 ・3、比較法 曲用Ⅱ 代名詞・数詞 4、代名詞 ・a、人称・敬称代名詞 ・b、指示代名詞 ・c、関係代名詞 ・d、疑問代名詞 ・e、その他の代名詞 ・不定代名詞 ・所有代名詞 ・再帰代名詞 ・相互代名詞 ・f、代名詞的形容詞 5、数詞 4、代名詞 代名詞には多くの種類があるが、その変化は大きく分けて同一変化 ...
サンスクリット文法編2~曲用Ⅰ 名詞・形容詞・比較法~
さて、本格的な文法に入っていきましょう……といいたいところなのですが、ここから先の曲用及び活用に関してはその変化を一つひとつ見ていくとそれこそ膨大なページ数にのぼってしまいます。 ですので、毎度書いていることですが、ここではその中で代表的なものだったり頻出するものだったりをピックアップするに限り、変化の詳細については文法書等を当たってください。また、煩瑣になるのを避けるため、説明も基本的なことに留めますので、例外や少数例に関しても同上です。 また、今回より今後文献講読的なことをやる際、文法解釈などで ...