さて先日、数学史上屈指の難問『リーマン予想』がついに解決されたかという話題が世界中を駆け巡りました。
cf,ついにリーマン予想が証明された!? (とね日記)
その後の数日間で一気に雲行きが怪しくなり、今では話題にも上がってこなくなってしまい個人的にはちょっと残念なのですが、私自身長らくその予想がどういうものかということに興味があり、今回は個人的な復習の意味も兼ねて『リーマン予想』について書いてみようと思います。
私が学生の頃(2000年代あたま)、『リーマン予想』と並んで長年解決されてこなかった『ポアンカレ予想』の解決論文が提出され話題になりました(後、2006年に最終的に解決が宣言されました)。
今回の『リーマン予想』や『ポアンカレ予想』は、2000年にアメリカ・クレイ数学研究所が100万ドルの懸賞をかけた7問の未解決問題『ミレニアム問題』に含まれており、私も『ポアンカレ予想』を扱う位相幾何学を副専攻という形で勉強していたので俄然好奇心をそそられたこともあって、『ミレニアム問題』各問がいかなるものかと当時独自で勉強したのですが、その時のノートを参考に文系の人向けにおおざっぱですが『リーマン予想』の解説を試みようと思います。
例によって、数学好きが高じて副専攻していただけで私も専門領域ではないので、もし詳しい方がいらっしゃれば記事への指摘などいただければ幸いです。

19世紀を代表するドイツの数学者ベルンハルト・リーマン(Georg Friedrich Bernhard Riemann 1826.9.17~1866.7.20)が1859年に発表した論文(『Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse<与えられた数より小さい素数の個数について>』)の中で、「証明できなかったが」という前置きとともに
「ゼータ関数\(\zeta(s)\)の非自明の零点は、全ての実部が\(\frac{1}{2}\)の直線上に存在する。」
と記した予想のことを指します。
正直これだけではなんのことやらさっぱりわからないと思うので説明しますと、この論文は素数の分布に関するリーマンの研究を記したもので、この中でリーマンは18世紀の数学者オイラー(Leonhard Euler)が研究した素数に関する級数をゼータ関数\(\zeta(s)\)とし独自の手法をもって複素数全体への拡張を行いました。
$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$
上述の予想内\(\zeta(s)\)はこのような形をした関数なのですが、リーマンはこれが\(\zeta(s)\)=0となる複素数sは全て\(\frac{1}{2}\)+(実数)×i、つまり複素平面のx=\(\frac{1}{2}\)の直線上に全て出現するだろうと予想したのです。「非自明の零点」というのは、この\(\zeta(s)\)に関しかつてオイラーの発見によって知られていた「sが負の整数の場合\(\zeta(s)\)は有理数となり、sが負の偶数ならば\(\zeta(s)\)=0となる」という零点が実はこれ以外にも無数にあることをリーマンが新たに発見し、この負の偶数以外から導かれる零点のことを指します。
予想が出されてから150年以上経過していますが、この間、コンピュータの発展などと相まって\(\zeta(s)\)の零点は現在までに10兆個も見つかっており、そのすべてがリーマン予想を満たしていることが証明されています。しかし、この零点は無限にあるので10兆個といってもやはり有限に過ぎず「たかだか10兆個」という感じなのです。
ちなみに「帰納法で……」とか言い出す方もいるかと思いますが、当然使えません(なぜなのかと解説すると長くなるので、そう思った方は高校の数学からやり直して集合論あたりを探ってみてください)。
cf,数学的帰納法 - Wikipedia
さて、バリバリの文系の方だともうすでにお手上げという感じかもしれません。しかし一歩進んで理解するために予想が成されるまでの経緯やキーポイントをかみ砕いてみていきましょう。
この予想の根幹にある素数P(Prime number)について復習してみましょう。
まず小学校で「(2以上の自然数Nの中で)1と自分自身でしか割れない(約数をもたない)数」と習ったのを覚えているでしょうか?
小さいほうから見ていくと2,3,5,7,11,13,17,19,23,29……とこの時点ですでに不規則極まりない形であることがわかります。もう少し詳しく見ていくと、素数における偶数は2しかなく、また一度現れた素数の倍数は素数ではないというのも特徴です。当たり前といえば当たり前ですが、こういう基本的なふるまい方をみていくと、小さな数でも不規則な形がだんだんと大きくなるにつれてさらに複雑怪奇になっていくことが容易にわかると思います。また素数が無限個あることは古代ギリシャのユークリッドが証明を与えています(『原論』第9巻 命題20)。
論理性が求められる数学にあって、この不規則極まりない素数は実に異質な存在だといえます。
19世紀になって当時の大数学者ガウス(Johann Carl Friedrich Gauß)は素数の濃度(ℵ)(ある集合内での素数の分布)について面白い予想をします。
それは「N以下の素数の分布は『Nのケタ数-1』に反比例する」というものです。
例えばNが10から100に変化した場合、「ケタ数-1」は1から2と2倍になりますがその分布は40から25へとおよそ半減します。実際N=10までの素数は2,3,5,7の4個ですので、N=100に移れば40になると予想できますが、実際にはN=100の場合、2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97の25個になります。しかし素数自体無限にあるので、この規則性が大きな数になってもそのまま適応するとは言い切れません。
このガウスの予想は後年証明されてからは素数定理と呼ばれ、「N以下の素数の個数はおおよそNの自然対数でNを割ったものと等しい」つまり、N以下の素数の個数を\(\pi(n)\)とするとnが十分大きいとき、\(\pi(n)\)は\(\frac{n}{\log n}\)と近似するというものです。リーマンが目指したのは他でもないこの素数定理(同時代的には素数予想?)の証明でした。
次に、素数の問題がゼータ関数へと導かれた過程を少し辿っていきましょう。
17世紀の数学者によって提出された級数に関するある問題がありました(Pietro Mengoli 1644)。
それは「平方数の逆数全ての和はいくつか」というもので
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\lim_{n\rightarrow\infty}(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2})$$
と記すことができます。
この問題を解決したのが先にも登場したオイラーです。
※証明方法については以下のリンクを参考にしてください。
バーゼル問題の初等的な証明 -高校数学の美しい物語
オイラーはこの答えを\(\frac{\pi^2}{6}\)と導きだしました。自然界でもっとも美しいとされる円に密接に関わりながらその実は無理数という円周率が自然数に関わる和に出現するということに、当時の数学者たちはさぞ驚いたことでしょう。この点に関しては以下の著書に詳しい説明がされているので興味のある方はご一読をおすすめします。

さて、オイラーは更にこの数式が一般の実数に対してどのようなふるまい方を見せるのかということを研究しました。つまり先の数式の指数2を含めたs乗数の実数nの関数と考えたのです。
$$\sum_{n=1}^{∞}\frac{1}{n^s}=\lim_{n\rightarrow\infty}( \frac{1}{1^s}+\frac{1}{2^s}+ … +\frac{1}{n^s})$$
こうしてオイラーは「s乗数の逆数の(無限)和」を考察していったのですが、そこで次のことが明らかになりました。
1)sが正の偶数ならこの式は\(\pi^s\)×有理数
2)sが負の整数なら式の値は有理数となり、sが負の偶数の場合値は0
3)この式はsと(1-s)の間で特別な関係性を持ち、実数\(\frac{1}{2}\)を中心とした対称性を持つ
このことは後の数学者たちによって更に研究が深められていくことになるのですが、その一方でオイラーはこの式が全ての素数を用いた別の形で表現できることを発見しました。それがいわゆるオイラー積と呼ばれるものです。
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a(n)}{n^s}=\prod_{p:prime}\frac{1}{1-\frac{a(p)}{p^s}}$$
これがなぜ等号で結ばれるのかを少し解説すると、
まずa(n)=1として左辺を素直に展開すると
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{6^s}+\cdots$$
となります。この時、右辺の整数を因数分解しておくと、
$$\frac{1}{(1)^s} + \frac{1}{(2)^s} + \frac{1}{(3)^s} + \frac{1}{(2^2)^s} + \frac{1}{(5)^s} + \frac{1}{(2\cdot 3)^s}+\cdots$$
となるのですが、これは各素数ごとに因数分解できることに気づくでしょうか?
$$\begin{eqnarray} &=& \left(\frac{1}{1^s}+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{2^{2s}}+\frac{1}{2^{3s}}+\cdots\right) \\
&& \times \left(\frac{1}{1^s}+\frac{1}{3^s}+\frac{1}{3^{2s}}+\frac{1}{3^{3s}}+\cdots\right) \\
&& \times \left(\frac{1}{1^s}+\frac{1}{5^s}+\frac{1}{5^{2s}}+\frac{1}{5^{3s}}+\cdots\right) \\
&& \times \left(\frac{1}{1^s}+\frac{1}{7^s}+\frac{1}{7^{2s}}+\frac{1}{7^{3s}}+\cdots\right) \\
&& \times \cdots \end{eqnarray}$$
これは算術の基本定理または素因数分解の一意性という約束事が適応されます。
cf,算術の基本定理 - Wikipedia
ここから
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s} = \prod_{p:prime}\left(1+\frac{1}{p^s}+\frac{1}{p^{2s}}+\frac{1}{p^{3s}}+\cdots\right)\tag{1}$$
という式を得ます。
右辺の積の中が無限和のままでまだ煩雑なので
$$1+\left(\frac{1}{p^{s}}\right)+\left(\frac{1}{p^{s}}\right)^2+\left(\frac{1}{p^{s}}\right)^3+\cdots$$
と変形させたうえで\(r=\frac{1}{p^s}\)と置き換えると
$$1+r+r^2+r^3+\cdots$$
というシンプルな形が得られます。
これを初項1、公比rの等比数列の和と考えると高校で習う無限等比級数の収束条件を満たすので、
cf,無限等比級数の収束,発散の条件と証明など - 高校数学の美しい物語
これを踏まえて\(r=\frac{1}{p^s}\)の置換を解いてあげると
$$1+\frac{1}{p^s}+\frac{1}{p^{2s}}+\frac{1}{p^{3s}}+\cdots = \frac{1}{1-\frac{1}{p^s}}\tag{2}$$
という形を得られます。
よって(1)(2)から
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}=\prod_{p:prime}\frac{1}{1-\frac{1}{p^s}}$$
を得ます。
少し長くなってしまいましたが、これに先のバーゼル問題のs=2を当てはめて計算してみると等号で結ばれるのが容易に想像できるでしょう。
これはオイラーだからこそ見抜けた妙だと思います。そしてこの式の最大の価値はまさしく「整数と素数をつなぐ架け橋」だったことといえるところです。
最初の方でも見た通り、まったく出現が不規則で無秩序な存在であった素数が整数と結びつき、sが正の偶数の場合に至っては円周率\(\pi\)とも関係をもつという事実。なんとも魅力的な話しだと思いませんか?
いよいよリーマンの登場ですが、先にリーマン予想が記された論文を紹介しましたが、リーマンはその短い生涯で膨大な量の仕事をこなしていながら数論に関する論文は実はこの一本しかありません。しかも10ページに満たないこの論文は研究「速報」的な扱いだとする見方が強く、実際には相当なページ数におよぶ詳細な大論文が期待されていながらリーマンは結局それを果たせず39歳の若さで没しています。実に惜しいことだと思います。
さて、リーマンが素数に関して行った研究は、前述の通り「素数定理」の証明でした。
リーマンはN以下の素数の個数\(\pi(n)\)をオイラー積を利用することで求めようと考えたのですが、その際オイラー積を複素関数で扱う必要が出てきました。そこで複素数sの関数で1よりも大きい実数の場合、
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a(n)}{n^s}=\prod_{p:prime}\frac{1}{1-\frac{a(p)}{p^s}}$$
の値に等しい関数を発見しました。それをゼータ関数\(\zeta(s)\)と定義し、また実数が1以外の場合においても「解析接続」という手法を用いることで複素数全体へと意味付けの拡張を果たしました。
本来ならここで複素数上で関数を扱えることとはどういうことか、その重要性を説明すべきなのですがあまりにも長くなるので別の機会に譲りたいと思います。
なにはともあれ、無事複素数上で\(\zeta(s)\)を扱えるようになったが、この意義としては、全ての素数に関する情報をゼータ関数という一つの関数に内包させたというところにあります。つまりゼータ関数のふるまいかたを解き明かすことは素数の本性を解き明かすこととほぼ同意義になったと言えるのです。
ではそのゼータ関数に関して、なぜ零点の位置を探るのか?
ゼータ関数の値が0となる零点は、sの実部が負の場合は『自明な零点』として、またsの実部が「1より大きい場合」「s=0の場合」には零点を持たないということは証明されてきましたが、それ以外の場合、つまり0,1を除く\(0 < s < 1\)の範囲(臨界領域)において零点がどこにあるかということがわかっていない、つまりとても重要な情報が欠けているのです。
そこで例の論文の中でリーマンは研究の結果をもとにその零点が\(\frac{1}{2}\)の直線(臨界線)上にあるだろうという予想を立てたのです。
結果的にリーマン自身もこの予想の証明には失敗し、また件の素数定理は後に他の人の手によって証明されましたが、その証明に挑む過程で副産物的に生み出された『リーマン予想』は本来の目的だった素数定理を凌駕するほど重要な問題として後代の数学者たちに残されました。一時期は「リーマン予想は数学者のキャリアをすべて打ち砕く」などと揶揄され研究に取り組むことさえタブー視されたこともありましたが、近年では当代屈指の数学者アラン・コンヌ博士が自身の『非可換幾何学』との類似を指摘したり、また物理学など他分野との関連も報告されるなど、にわかにその研究が再燃・再加速した装いがあります。
そして先日の解決されたかという報告。この数学史上の難問は、これから先もまだまだ人々を魅了しつづけてくれそうです。
以下、もう少し詳しく知りたいという方のための参考文献です。
理数系の方は問題ないレベルだと思いますが、文系の人だとちょっと敷居は高めだと思いますが理解がより一層深まります。
 リーマン予想とはなにか 全ての素数を表す式は可能か リーマン予想とはなにか 全ての素数を表す式は可能か |
 リーマン予想の150年 (数学、この大きな流れ) リーマン予想の150年 (数学、この大きな流れ) |
 大学入試問題で語る数論の世界―素数、完全数からゼータ関数まで 大学入試問題で語る数論の世界―素数、完全数からゼータ関数まで |
一応文系の人向けということでかなりおおざっぱに書いたので、本当の意味で『リーマン予想』を解説するには、複素数のこと、数列の収束のこと、集合論(特にイデアル理論)、ガンマ関数やフーリエ変換など、まだまだ必要な知識がたくさんあります。そのためにはさらに詳細な解説をしていかないいけなくなります。それでも文系の中でも特に数学が苦手だったという人たちには厳しいものがあると思います。
しかし、これは個人的にことあるごとに言ってる持論ですが「数学は最終的には国語の問題」なので、視点を変えれば恐るるにたりないものだとおもいます。
言葉がたまたま数式や記号に置き換わっただけの話しなので、なんのことやらわからない数式も、その一つひとつの意味を解釈していけば文章そのものともいえるのです。また、問題そのものもある日突然出てきたのものではなく、長い歴史の中でいろんな学者がさまざまな研究を積み重ね蓄積した結果登場したものなので、それ自体が分からなくてもその歴史を紐解くことで理解が深まったりするものです。
苦手なものでも、少しでも興味が湧いたのならまずは自分が分かるところまで落とし込んでいくというのは、どんなものを学ぶ上でも非常に有効な手段だと思います。
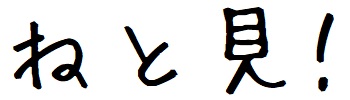
 Newtonライト『素数のきほん』
Newtonライト『素数のきほん』