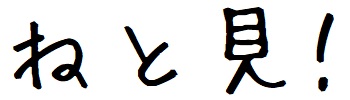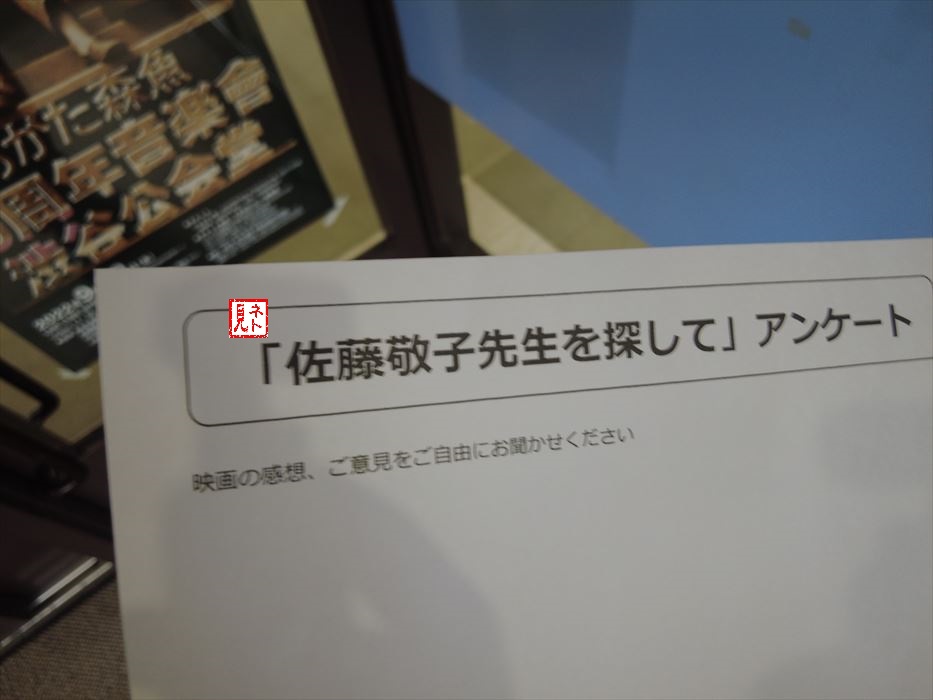
目次
Amazon
愛は愛とて何になる
◎前説
8月上旬、私は農作業の傍らで北海道のローカルラジオ番組に耳を傾けていた。
その番組の一コーナーにとあるミュージシャンがゲスト出演していたのだが、なにやら熱心に口角泡を飛ばす勢いで必死に言葉を紡いでいる。件のコーナーでは、さまざまなミュージシャンのメッセージが流されたりゲスト出演した後で楽曲が放送されるのだが、その日に限ってはなかなか曲に移らない。最終的に楽曲は流されないままトークだけが弾み、コーナーを終えた。この時のミュージシャンこそ、他でもない「あがた森魚」その人だ(※1)。
北海道留萌市に生まれ小樽・青森・函館で育ったあがたさんは、吉田拓郎・泉谷しげる・友部正人とならび新進気鋭の「ニュー・フォーク」シンガーとして活躍した。デビューシングル『赤色エレジー』は50万枚を売り上げ一躍時代の寵児として名を馳せた。大正・昭和の雰囲気漂うロマンティックにして哀愁のある楽曲は独特な世界観を醸し出し、「フォーク界の異端児」と称されることもあった。80年代には「ヴァージンVS」を結成し、テクノ・ニューウェーブミュージックへも進出し、90年代には『雷蔵』でワールドミュージックにまでその裾野を広げている。他方、映画監督や俳優としても活動するなど、マルチタレントの走りともいうべき多方面でさまざまに才能を開花させた異色のミュージシャンだ。
そんなあがたさんが何をか熱心にラジオで語っている。
「北海道の短い歴史」「それ故のフットワークの軽さ」「北海道だからこそ出来、発信しうる表現」
ご自身「最近は歳でなかなか言葉が出てこない」と謙遜されていたが、私にはそれが一つひとつの言葉を必死に絞り出しているように聴こえ、ふと「これはなにかありそうだ……」と感じずにはいられなかった。その「なにか」は明確には分からない。しかし妙に心揺さぶられるのである。
8月19日、6年の歳月をかけ撮影されたドキュメンタリー映画『佐藤敬子先生を探して』が小樽市で先行上映されるという。これは実際自分の目で確かめてみるしかない。私は大雪山の麓からノコノコと出かけていくことにした。
あがた森魚『赤色エレジー』(2009年11月22日「青梅宿アートフェスティバル」~勝沼3丁目の夕日ステージ~より)
(約5分10秒)
Amazon

赤色エレジー (小学館文庫)
◎映画『佐藤敬子先生を探して』
北海道小樽市。道内外から多くの観光客が訪れるこの街は、北海道はもとより日本を代表する観光都市といっても過言ではない。
今年、新型コロナウイルスの世界的流行後はじめて行動制限を伴わないお盆を迎え、街は観光客で賑わっていた。

私の友人知人に小樽の出身者は多い。だがそれを除けば縁もゆかりもない土地である。主だった観光名所はこれまで巡ったことはあったが、今回の映画上映の会場である小樽市民センターには初めて足を踏み入れた。その中の最大施設・マリンホールは450超の座席数をほこる。
ラジオはじめ様々なメディアでの告知、また「あがた森魚」というネームバリューもあるが、果せるかな実際は客席の半分も埋まっていなかった。盆明けとはいえ金曜日の17時開演、そんなスケジュールも影響しているのだろう。だが、関係者はじめ往年のファン、そして私のような突飛な人間も含め、会場には「あがた森魚」を基軸とした独特な空気が漂っていた。

さて本題の映画『佐藤敬子先生を探して』。
舞台はあがたさんが小樽で過ごした1950年代と現代の小樽を行き来する。同級生、佐藤先生の元同僚、あるいは親族。佐藤敬子という一人の人間を取り巻いたさまざまな人物の証言が重層的に、そして敷衍的にストーリーを形作っていく。あがたさん自身の懐古を下地に、佐藤先生の人物像を抽出・彫像しようとする試み高い作品と見えた。
だが、件の佐藤先生の姿を追い求める中で浮き彫りにされたのは、「小樽」という一地方都市が孕んでいる歴史と現状だった。
小樽は明治時代にはじまった北海道開拓とともに成長してきた街である。その歴史は古く、集落の形成という点では縄文時代にまで遡る。江戸期には松前藩の商業地として、また明治の開拓期、本府が札幌に置かれることが決まると小樽は北海道の海の玄関口として発展した。道内初となる鉄道が敷設され、名実ともに経済・文化の中心都市となった。「異世界を孕む地域」、それが小樽という街の素地にある。なにより小林多喜二や伊藤整といった文学者をはじめ、多種多様なジャンルの文化・芸能・学術人を輩出してきたこの街は、その感受性を育む上で必要十分だった。
しかし時代を経る中で、次第に札幌が中心都市としての責を担うようになり、また道内産出のニシンや石炭の需要減少、石狩湾新港への機能移転と相俟って漸次衰退の一路を辿っている。かつては20万人を誇った人口も、現在では10万人前後で推移している(※2)。
今でこそ小樽は一大観光地だが、経済的発展と衰退の波間を揺れ動き、いわゆる「運河論争」を経て現在のような観光都市になった経緯は他所ではあまり知られていない。本編中にはその渦中にあった人々の証言が報告されているが、そこには小樽という例示の中に、地方都市あるいは北海道という土地が潜在的に孕んでいる運命的背景のようなものが見えた気がした。
一方、この作品の本来の基軸であるあがたさん自身の人生、そこにはいろいろなものをつかみながら形にしてきた「ひとつの時代」が見えてくる。先述の通り、ストーリーそのものは、小学時分の担任教師の姿を求めるかつての教え子をめぐる近縁だ。
件の佐藤先生に対し、その人物像は「聡明で、綺麗で、怖くて、ザンコクで」と語られている。2000年代初頭に発表された楽曲『佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど』にも詳しいが、今回の映画の中で、その"ザンコク"さは「『海底二万哩』をみせたこと」「ヤギ乳を飲ませたこと」「先生の理想、そして何を成就したかったのか教えてくれなかったこと」の三点に集約されていた。個々のエピソードは作品内で幾度となく回想されているので割愛する(面白いので是非機会があれば鑑賞していほしい)が、三点目の「先生の理想」「何を成就したかったのか」について、私自身の感想も含めて少し記したい。
まず率直に感じたのは、佐藤先生はあがた少年にとっての初恋の相手なのだろうことだ。作品中、明確に言及はされていない。しかしその後の人生において、自身の恋愛観や女性観を形作った人であることは間違いないだろう。語りはもちろん、多くのエピソードやコラージュ映像からもそのことは容易に想起された。その中でもひときわ印象的だったのが、テーブルに肩ひじ付きながら窓外を眺める佐藤先生の姿、「聡明な女性のアンニュイな横顔」……。おのずと楽曲『佐藤敬子先生は~』の中にあるこんな歌詞が呼び覚まされた。
「夏のテエブルで とおい灯台をみつめてました」
「とおいどこかへ消えてしまいたかった夏」
このエピソードに、私はひどく心を揺さぶられる気がした。それはあがたさん自身の恋愛観や女性観を超越した、なにかひとつの大きなヴィジョンのように感じられたからだ。
「先生の理想」「何を成就したかったのか」……。先生の口からあがた少年に直接語られることはなかった。しかし、先生は"教師"という生き方、立場、そして姿勢の中で、あがた少年にそのことを表現していたのだろう。
「生きていること、それ自体が表現ということ」という考え方に、私もこれまで幾度となく触れてきた。店屋であっても、職人であっても、会社員でもアルバイトでも、文学でも、浪人生でも、絵画でも、ホームレスでも、専業主婦でも教師でも、音楽でも……。生きていることそのものがその人の生き様を描き出した表現。恩師・佐藤敬子先生という一つの表現を受け取り、ミュージシャン・あがた森魚という一つの表現につながっている。そしてそのつながりは時や場所を選ばず連綿と続く。
その一人ひとりの人生という表現が、作品中、あがたさんの母校・入船小学校の閉校式のシーンに昇華されているように感じた(※3)。
閉校式にゲストとして参加したあがたさん。特別ライブの時間も設けられ、当時の在校生の前で楽曲を披露した。このシーンでふと私は「年の離れた先輩後輩とはいえ、相手は小学生……そこにあがた森魚!?」とハラハラさせられた……が、そんな杞憂は次のシーンで見事に打ち破られた。大盛りあがりの在校生たち。それぞれに手を叩いたり身体を動かしたり、あがたさんのコールにレスポンスしていたり……。一抹でも不安を脳裏によぎらせた自分を恥じた。それはともかく、このシーンには先述の佐藤先生という人生の表現、あがた森魚という人生の表現、そして生徒一人ひとりに託された人生の表現、その壮大なバトンリレーが見事に結実したような印象を受けた。
これは余談だが、上映会後の質疑応答の際、当時入船小学校で閉校式の準備を担当されていた先生がマイクを握られ、当時のエピソードを語ってくれた。曰く、あがたさんのゲスト出演が決まって生徒に大々的に発表したところ、生徒たちは案の定「あがた森魚?だれ?」という反応だったらしい。致し方のないことではあるけれど、しかし実際当日を迎えてみると、作品中のシーンのごとく生徒たちは大盛りあがりだったという。もちろん事前に生徒たちにあがたさんの略歴や楽曲を教えたわけではなきあったという。しかし生徒たちは、"ぶっつけ本番のあがた森魚"の魅力にドンドンと惹かれていったというのだ。そうだ、あがた森魚の音楽にはそうした不思議な魅力と魔力が潜んでいる。
さて、話しを戻そう。見事に受け継がれそして相互に影響を与えた表現のバトンは、当日この作品を観覧したすべての人にも同様に受け継がれたのだと思う。私はそう信じたい。
あがたさんはこの作品を「自分自身、自画像」「いまの時代への回答と投影」と語っていた。しかしその根底には「作りたくて作った」「あがた森魚をとして撮りたくて撮った」作品であり、「自分が小樽で得たものを形にしたい」そんな思いが滔々と流れている。
2017年9月の撮影開始以来、足掛け6年の歳月を経て完成した映画『佐藤敬子先生を探して』。
佐藤先生の話しや小樽の話しの他にも、2011年の東大震災後から始まった活動、コロナ禍の中で産まれた「タルホピクニック(※4)」など、あがたさん自身のこれまで、現在、そしてこれからの活動についても紹介されている。これもまた、あがた森魚を知る人には魅力的なシーンばかりだ。
なにより、これまで一度でもあがた森魚の音楽がもつ不思議な魅力と魔力、そしてそこから湧き出る中毒性を感じたことのある人には、是非とも鑑賞してほしい作品だと感じた。決して万人受けするような作品ではない。コラージュやイマジナリーといった映像的レトリックも多く、ドキュメンタリー映画でありながらかなり実験的な要素も多い。しかし、あがた森魚というミュージシャンのその淵源の一端に触れられる貴重な作品であることは間違いない。そしてできれば、人生という表現のバトンを一人でも多くのひとに受け取ってほしい。
あがた森魚『佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど』(2001年6月17日 ~山田勇男個展「六月の夜の夢の切れっぱし」~より)
(約6分10秒)
Amazon

佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
◎私にとっての「あがた森魚」という人
さてここからは、個人的な思い出といくつか思いついたことを書いてみたいと思う。
私がはじめて「あがた森魚」というミュージシャンを知ったのは、いつの頃、なにがきっかけだったかというと、小学生時分に行き着く。私の音楽的な好みに多大なる影響を与えた人やグループは数多いが、その中でも群を抜いて感化されたのは植松伸夫さんの音楽だ。いわずとしれた名作ゲーム『ファイナルファンタジー』シリーズ、その音楽を世に送り出したゲーム音楽の第一人者。そんな植松さんのエッセイ集(※5)の中に、「あがた森魚」の名前が記されていた。
若き日の植松さんは、友人に誘われる形でアルゼンチンタンゴのバンドに所属していた。そのバンドが本場アルゼンチンで公演を行った際、ボーカルとして参加したのがあがた森魚さんだったという。あがたさんのボーカルとして資質、公演先での反響とハプニング、そして植松氏とあがたさんとの語らい……。若き日の植松さんがあがたさんからどれほどの刺激を受けたか、それがよく分かる情熱的な書き口が印象的だった。ちなみに、このエッセイ集は植松さんが製作したアルバムの特典なので、非売品である。他のエピソードもとても面白く、植松ファンなら是非とも手元に置いておきたい一冊だ。なんらかの形で再販してもらえないだろうかとずっと思っている。閑話休題。
それからしばらくして中学生になった頃、私は60・70年代の音楽に相当な興味をそそられていた。90年代後半、もうその頃でも「懐メロ」と称されていた時代の音楽。現在のようにインターネットもそこまで普及しておらず、音楽配信・動画配信などというサービスが出てくる未来さえ予想できない頃。ましてや私は北海道の山の中に生まれ育った。当時隆盛を極めていたレンタルビデオ屋なんか、遠く離れた都会の代物。そんなものだから、テレビで60・70年代の特番なんかがあると貪るように見ていた。
そんな折、たまたま見ていた番組でやはりあがたさんが登場した。伝説の名曲『赤色エレジー』をその時はじめて聞いた。正直なところ、「この人があがた森魚か~」と感慨深くテレビ画面を眺めるとともに、「なんか物悲しい歌だなぁ」とぼんやり思った程度だったことは白状しておこう。
これと同じ頃、植松さんと並んで私の音楽的指向性に多大なる影響を及ぼしたYMOを貪るように聞いていた。父がYMOのレコードを数多く持っていたので、CD~MDが主流の時代にあって、私はひたすらレコードに針を落としていた。
YMOといえばいわずと知れた伝説のグループ。テクノ音楽の先駆けとして世界を席巻したことはあまりにも有名だ。もちろん今でこそ、細野晴臣・高橋幸宏・坂本龍一というこの三人がそろっているのだから売れないはずはない、と思うけれども。それはさておき、YMO、特に細野さんの著作やインタヴューなんかに接すると、たびたび目にした名前があった。他でもない「あがた森魚」だ。先の『佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど』の歌詞にもある通り、あがたさんと細野さんは若い頃より旧知の中である。
ざっくりとではあるが、子どもの頃から今に至るまで、自分の音楽的興味に影響を与えた人物や出来事、その背景には常にあがた森魚というミュージシャンの陰がチラついていたのだ。……とはいえ、自分から積極的にあがたさんの音楽に触れに行ったことはなかった。その一方で事あるごとにその名前と音楽に接する。イメージとしては、物理学の二重振り子によるカオス現象のような感じだろうか? 間接的ではあるが、なにか蜘蛛の糸のような細く長い不思議なご縁の糸を結んでいただいているような気がしている。
今回の映画上映会にしてもそうだ。たまたま聞いていたラジオ番組にたまたまあがたさんがゲスト出演されて、たまたまそれを聞いていた自分が心に引っ掛かりを覚えて……。「いまから思い返せば」ということで若干のバイアスがかかっていることは否めないだろうが、本当に不思議なご縁を感じる人なのだ。
上映会終了直後、あがたさんはロビーで会場のお客さんを出迎えていた。私が会場から出た頃には、地元の関係者の方たちだろうか、輪になってなにやら親しげに言葉を交わされていた。遠くから見ると、どこか同窓会の名残りのような雰囲気で、その光景に心温かくなるのを感じた。私はというと、しばらく待っていれば自分もあがたさんと言葉を交わす機会を得られたであろうが、その時はすぐに会場を後にした。「きっとこの人とはまたどこかで巡り合うだろう……」あがたさんご本人を目の前に、そこでもやっぱりそんな気がしたからだ。
……しかしどうしたことか、件の映画を観終わったあとから、どうしても心が揺さぶられて仕方なかった。件の映画の告知をラジオで聞いたとき以上にざわついている。表現すること、自分の中にうごめくなにかを表出することの重要性と重大さ、そこにのしかかる責務の計り知れない重荷をまざまざと見せつけられた気がした。それは先に書いた「バトン」のなのかもしれない。表現すること、伝えること、そのバトンを自分もまたしっかりと受け取ったということなのだろうか? 自分自身、子どもの頃は小説家になりたくて文学青年よろしく日々を過ごした。今では若干方向性は違えど、やはり文章を書くことに執着しそうした活動も続けている。……とはいえ、今回の映画で受けた衝撃をロジカルで明晰な言葉を以て表現できないことに歯がゆさを覚える。そもそも、文章構造を意識しながら日々書き散らしているが、今回ばかりはどうもいつも以上に書き散らかしたような感を否めない。実際、この『佐藤敬子先生を~』の映画を自分自身明確に理解できたとは言い難い。ただただ感じ取ることに必死だった。だが、ある意味でそれは、これからの自分の課題を明示しているのかもしれない。それ故の心の揺れ動きだと、今は思いたい。
遅い夕食をとったあとで小樽の街のメインストリートに足を踏み出せば、夜の帳に煌々と燈黄色の街頭の灯りが映えている。海からの潮風と山辺から吹き下ろす風が綯い交ぜになって頬をくすぐった。
「あ、夏も終わりか……」
ふとそんなことを感じた。
小樽の街の港の夜は、しんと静まっている。

Amazon
あがた森魚コンサート~「永遠の遠国」at 渋谷ジァン・ジァン
余談
あがたさんの盟友・鈴木恵一さんが率いるムーンライダーズの『くれない埠頭』。この曲を聞くたびに中原中也の「港市の秋」という詩が自然と想起される。何故だか分からない。だが底流に同じ心情が流れているように感じられるのだ。個人的な印象として、『くれない埠頭』は淡い夕やけ空の白雲たなびく埠頭、「港市の秋」は絶叫に近い黄金色に照らされた鄙びた漁師街が心に浮かぶ。ムーンライダーズ『くれない埠頭』(1992年12月24日NHKホールライブより)
(約5分30秒)中原中也『港市の秋』
(中略)
「今度生れたら……」
海員が唄う。
「ぎーこたん、ばったりしょ……」
狸婆々がうたう。
港の市の秋の日は、
大人しい発狂。
私はその日人生に、
椅子を失くした。
Amazon
It's the moooonriders〔CD〕
≪脚注≫
飛鳥山タルホピクニック - MARTIN古池の 「街角の歌芸人」
■