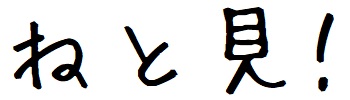極夜行
角幡唯介
出版社:文藝春秋
発売日:2018/02/09
人間の作り上げてきた文明の外に出る。そして真の闇の中を彷徨い、本物の太陽と出会うための旅の記録
北極圏において一日中太陽が沈まない「白夜」は、その奇異さからテレビ番組などでも特集されることも多いが、その正反対に一日中太陽が昇らない「極夜」があることを知る人はどのくらいいるだろうか?
日本で四季が起こる理由と同様、理屈で考えてみたら当然のことなのだが、言ってしまえば闇夜が来る日も来る日も続くという環境がテレビ的に映える訳でもないので、そう話題にのぼることもないだろう。
そんな闇の世界「極夜」において、グリーンランド最北の町・シオラパルクから北極海を目指した冒険家による紀行文。
個人的に、今年読んだ本の中でも一、二を争うほどワクワクしながら読めた本だった。
北極圏を旅した冒険家による紀行文は、故・植村直巳さんはじめ国内外の多くの冒険家が記しているところだが、極夜を旅したというものはなかなか見ない。
そんな本書をひとたび開けば、そこには一面見渡す限りの雪原、極寒に孤独、野生動物へ恐怖や熾烈極まりないブリザードなど、普段日本で生活している者にとっては想像もできない、壮絶で苛烈な極夜の世界が広がっている。
元新聞記者である著者の筆力ある描写もまた的確で、極限的な状況に翻弄され続けた姿には、読む側に圧倒的な衝撃を残してくれる。
著者はこの旅のために四年という歳月を準備に当てるなど、並々ならぬ意欲で挑んだということは前作にあたる「極夜行前」などに詳しいが、本書ではそこからつながる内省的な部分――冒険家として、この旅に求めたものや道中の心理的な葛藤、果ては著者一流の妄想など、そうした感情的描写が多い点、他の冒険家による紀行文とは一線を画している。
広義での「旅」という行為において、そこで何を感じ何を得るかはもちろんひとそれぞれだが、本書のような極限的な状況での旅もまた、これを経験した著者だけにしかわからない世界だ。
その世界観をまさしく疑似体験したかのように感じられるのは、そうした著者自身の内省的心理的吐露があったからこそだ。奇跡的なくらい不運に見舞われ続け、生死の境目を綱渡りのように歩んだ冒険譚。極限の状態でいかに判断し、本能と理性を保ったか。そこから紡がれた言葉はいかにも骨太だ。
つまりある意味で本書は究極的な自己啓発本といえる。
Amazon
極夜行前