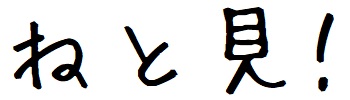在野と独学の近代-ダーウィン、マルクスから南方熊楠、牧野富太郎まで
志村真幸
出版社:中央公論新社(中公新書)
発売日:2024/09/19
「学問の自由」とはなにか?
近代イギリス-日本の学問におけるプロ・アマの立ち位置について、南方熊楠の半生を基軸に紐解いている本書。著者は熊楠研究の第一人者だが、熊楠に限らず、自分の興味関心の赴くままに学んだ人々の姿も描き出している。
イギリスで在野の研究者や独学者が学問の中心だった時代、大学や図書館がどのような機能を果たし、また民間でどのように学問が成熟していったかの課程は実に興味深い。一方の日本においては、文明開化の足音と共に官主導で学問の場が確立され、欧米のそれを輸入・吸収しつつ自らの教育課程として昇華していった背景がある。つまり、横の広がりをもって体系化されていったか、縦のつながりで体系化されていったか、この違いは後の教育現場の形成にも大きな影響を及ぼしている。
どちらが良い悪いというのではなく、学問というものの主導権をどこが持っていたのかはその裾野の広がり方に対して重要な意味を持つ。そういう意味で、日本の教育が官主導で成立していったのは状況の問題も孕むがいかにも日本的だと思う。
それ故にこそ、熊楠のように探求心の赴くまま広範な分野を学びたい学徒にとって、日本の学問の現場はあまりにも窮屈だったのだろう。その一方で、牧野富三郎や柳田邦男のように官民の狭間に身を置き続けた人物もいる。結果熊楠と訣別するに至るが、それぞれ一理あるのだから必然的と言わざるを得ない。
終章で著者は「イギリスを理想的に描きすぎた」と反省しているが、現代日本の大学教育の急速な衰退の姿を見るにつけ、昨今の独学・学び直しへの注目度の高さと相俟って、学ぶことの楽しさと重要性を投げかける意味では最適な理想像かもしれない。