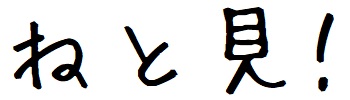浪人時代、新宿の紀伊国屋でたまたま見かけたのがきっかけだった。表紙には、作業現場と思しきその場所にはおよそに似つかわしくない雰囲気をたたえた初老の男性が、荷車に腰掛け読書している写真があった。「沖仲仕の哲学者」ことエリック・ホッファーその人だ。
この本は彼が沖仲仕として働いていた頃のある1年間の日記である。
仕事現場での作業の内容、友人家族との団欒、歯医者のこと……何気ない彼の日常がつづられたごくごく普通の日記なのだが、ところどころで思索と考察が織り込まれている。その冷徹なアフォリズムには驚嘆の声しかない。エリック・ホッファーは社会の基底の中で長らく人生を過ごした人だ。沖仲仕はじめ鉱山夫、農業労働者など、常に大衆の中を渡り歩いてきた。その彼の言葉には人間と社会を見る磨き抜かれた鋭い視線が感じられる。
15歳ころまでほぼ盲目。視力を回復したのちには失われた時間を取り戻すかのようにむさぼるように読書に明け暮れる。家族との別れ、自殺未遂、キリスト教への感化。……壮絶な半生が彼にそうした感性を持たせたのだろうか?
モンテーニュ『エセー』に魅せられ自身の思索を言葉にしたいという熱望は、名著『大衆運動』(原書 The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements.1951)で花開く。
彼はその後も飽くなき探求を続けつつも、常に一労働者として大衆の中にあった。
正直なところを言うと、そんな彼の姿に私は大変憧れていた。
私自身大学で哲学を専攻していたが、今も昔も「哲学とは机に噛り付いてやるものではない」と思っている。むしろ、日中炎天下で肉体労働をして、夕方家に帰っては35度の焼酎をかっ食らいながら麻雀打って後は寝るという生活の方が余程哲学的な生活だと考えている(このことについては世にいう哲学者の先生方からも共感を得ているから、多分限りなく正解に近いものだと信じている)。
ホッファーの生活は、そのことと見事にマッチしていた。
在野で鍛え上げられたホッファーの知性は、研究室に閉じこもった学者たちのそれと違い、鋭利にして重厚だ。なにより、何十年も前に書かれたとは思えないほど、現代社会の諸問題を解決しうるに足る糸口を数多く含んでいる。
彼がどんな生活を送り、どう思考したのか。それを味わうためにもじっくりと読みたい一冊だ。
 エリック・ホッファー自伝―構想された真実 エリック・ホッファー自伝―構想された真実 |
 魂の錬金術―エリック・ホッファー全アフォリズム集 魂の錬金術―エリック・ホッファー全アフォリズム集 |