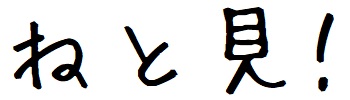読んでいない本について堂々と語る方法
ピエール・バイヤール 著 / 大浦康介 訳
出版社:筑摩書房(ちくま学芸文庫)
発売日:20216/10/06
実はムズカシイ"読まない"技術
知る人ぞ知る世界的名(迷?)著。人を食ったようなタイトルながら、中身は実に硬派。
大学で教鞭をとる著者は、職業柄日々膨大な書物や論文と格闘している。専門は精神分析とのことだが、本書は近代フランス文学の話題を中心として「読まずにコメントするという経験」について語られている。特に秀逸なのは、引用あるいは参考文献として挙げられている書物すべてに「<未>全く読んだことがない」「<流>流し読みした」「<聞>人から聞いたことがある」「<忘>読んだが忘れてしまった」という著者の読書体験の略号が附され、更に「◎とても良かった」「○良かった」「×ダメ」「××ぜんぜんダメ」という四段階の評価がなされている点だ。そこから分かることはひとつ、この本の著者はすべてまともに読んでいないか読んでも中身を忘れてしまっていることである! まさに虚を突かれたかのような事実。さすがに著者自身の著作を紹介しておきながら「<忘>〇(良い)」と附していたのには笑ってしまった。
しかしこのことは、愛読家ないし読者家にとっては実に感慨深い事実ではないだろうか?
著者は、書物の意義は「その内容」ではなく「外側に存在している」という。一冊の本の隣りにどのような本があるのか、そして他の膨大な本とどのように接続し関連しているのか。一冊の本を読んでいるだけでけではその本についてさえ語ることは到底できない。まさしく木を見て森を見ずの状態であることを指摘している。
本書中、著者の筆致は常に饒舌でなにか煙に巻かれているような巧妙なレトリックが潜む様相を感じる。だが引用・参考に挙げられている部分を除いて、著者一流の読書・書物論にだけ目を光らせていれば自然と霧は晴れてくる。そこで注目すべきは、著者の読書の質だろう。「読んでいない」にもかかわらず、論理は明晰だ。これはすなわち、教養あるいは批評・批判的精神とはなにかを暗示するとともに、受動的な読書に対する能動的読書の有意性を明確に指摘している。
書物とは「自己本来の考察の口実として」存在すると語る著者の指摘は鋭い。
ふと思い出した逸話だが、和辻哲郎が哲学者・井上哲次郎にとある本を借りに行った際、その本の内容について滔々とまくしたてられたらしい。だが実際和辻氏が読んでみると、井上氏の語っていたことは全く見当違いで「こんなホラ吹きが大学教授をしておるとは何とも情けない」と嘆いたとか……。
Amazon
思想のドラマトゥルギー (平凡社ライブラリー)