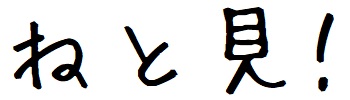生まれてこないほうが良かったのか? ――生命の哲学へ!
森岡正博
出版社:筑摩書房
発売日:2020/10/15
人生を"肯定"するための新しい哲学
近年、あらたな発展をみせる「反出生主義」。
「生まれてこなければよかった……」という心理は、現代人に限らず古代から多くの人が抱いてきた人間的ジレンマでもある。
本書はその反出生主義の在り方を、古今東西の哲学者や宗教を軸に掘り起こし、新たなる問題提起へと導く意欲作だ。反出生主義に対し真正面から挑んでいるという意味で、日本唯一にして随一の書籍。
反出生主義は「自分が生まれてきたことを否定する」思想と「人間を産み出すことを否定する」思想のふたつに大別されるが、本書は前者を重点的に検討している。
誕生否定の思想は古く、古代ギリシャに遡る歴史を持っている。
その中では、人間に対するそれに留まらず、動物や植物、果ては世界そのものにまで敷衍されるものもあり、幅広いグラデーションで展開されている。
本書はゲーテ『ファウスト』を導入に、ベネターやショーペンハウアー、古代インド思想から仏陀に至り、ニーチェでそのトドメを刺してくる。
なかなかに躍動的な論理転換が繰り広げられるが、叙述の軸が明解なので無理がない。
この流れを踏まえ、反出生主義への思考を単なる思想比較に留めることなく、未来の哲学的議論の創造を試み、新たな地平をつくるべく「生命の哲学」を提唱している。
ただ、この「生命の哲学」についての著者の主張に関しては、その実際は本書内に譲るとして、個人的にそれまでの流れに比して若干の弱さを感じずにはいられなかった。共感できるものの、もう少し深みのようなものが欲しいという雑感が残った。
これはもちろん、「生命の哲学」自体が生まれて間もないこともあり、まだまだ発展途上であることに他ならない。
また反出生主義という思想がまだ手付かずの議論を多く残しており、さらなる課題を生み出す余地をもっていることも手伝っている。
なにより、この思想の問いは常に一人称、つまり「私は」なのだから、こうして新たな議論の枠組みを提唱する著者もまた、自問自答し迷い続けているであろう姿がそこに求められた。
本書は「生命の哲学」プロジェクトのほんの序章に過ぎないという。今後の展開には大いに期待したい。