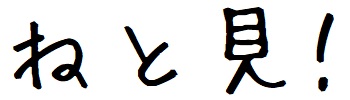赤松利市
鯖
出版社:徳間書店
発売日:2018/07/21
伝説の一本釣漁師たちをめぐる"欲"にまみれた愛憎劇
海の雑賀衆―
独自の釣法でその名を轟かせた紀州生まれの伝説の漁師集団は、戦国時代の傭兵集団「雑賀衆」に例えられそう呼ばれた。
しかしその技術も時代の趨勢とともに多く需要されるものではなくなり、いつしか知る人ぞ知るという存在に成り果てていた。
最後に残された5人が行き着いたのは北陸の小さな小島だった。
本作はそんな背景をもとに描き出された作者初の長編小説。
読み終えての感想は「久しぶりに人間臭い小説に出会えた」の一言につきる。
もっとも自分も昔ほど熱心に小説を読まなくなってしまったから、単純にこうした作品と出会える機会が減ったこともある。
それでも昨今の小説界隈にあっては稀有な力作だろう。
2018年、「62歳、住所不定、無職」の大型新人として文壇の話題をさらった作者。
その半生には、同じく作家の西村賢太さんとはまた違った破天荒さがある。
cf,色と欲で破綻した63歳男がつづる底なしの不幸 「ボダ子」を書いた作家の赤松利市氏に聞く
こうした人生の理不尽や不条理を通して気付きえた作者の言葉には、人間の核心を突くものがある。
愛、欲、狂気、破滅。……
謀略と裏切りの中、あまりに大きな劣等感をかかえた卑屈な人間の高揚と堕落。
その生臭さが読めば読むほど強烈に想起させられる。筆力も衰えず、最後まで怒涛のスピードで物語が進んでいくあたりも圧巻だった。
また登場人物たちの人間関係が、そのまま外交や政治の縮図のようにみえてくるあたりも実に巧妙だ。
昨今、小説はじめマンガも読まないという人が増えているというが、その理由のひとつに「他人の妄想話しなんか読んでいられない」というものがあるらしい。
たしかに最近の小説には破天荒なストーリーであったり、あるいは読者をあっと言わせるようなケレンに満ちた書き口だったり、あるいは息もつかせぬ怒涛のようなテンポだったり、そうした表面的な技巧ばかりが注視され読んでも中身をなにも感じない作品が多いような気がする。もちろん小説の技法としては大切なことではあるけれど、そうした「いかに書くか」という部分に終始した作品があまりに多く、結果「妄想」そのものが小説として出回っている感が否めない、そう感じている。
小説の面白さあるいは醍醐味のひとつには、自分が経験したことのない事柄や感覚の追体験、自分の人生や感覚の中にないものを作品を通して味わい知ることがあると私は考えているが、その追体験を容易たらしめるために「いかに書くか」という技法があるのであって、小説にとって本当に大切なのは「なにを書くか」なのではないだろうか?
本作のように骨のある小説らしい小説が、現代にもっと出てきたならきっと人びとの感覚も変わってくるのだろう。
Amazon らんちう |
 どうで死ぬ身の一踊り |