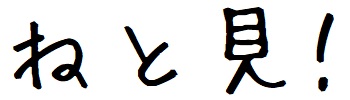出版社:彩図社
発売日:2010/11/24
不世出の詩人・中原中也の心象風景に触れる詩編
本家の羅列ニュースのコメントなどで時々書いているが、わたしは太宰治が嫌いだ。
正確には太宰はじめ無頼派作家の生き様が好きではない、といったところだ。彼らの私生活は破天荒そのもの。それでいて至極マットウなことを語っている。無頼漢な生き様とは裏腹に、その内面は実に真面目で確固たる信念がある。そこが彼らの魅力そのものなのだろうけど、個人的に到底受け入れられない。不良の格好をした好人物は、結局のところ好人物でしかない。
無頼派が好きになれない理由のその根底には、彼ら以上にこの稀代の詩人・中原中也の言葉に深く感銘を受けたこともあるだろう。
これは三島由紀夫などにも言えることなのだが、中也は生き様も言葉も、徹底的にグレている。大真面目にグレている。
「こうするっきゃかない!」「こういう生き方しかできないんだ!」詩にうつつをぬかしていなければもうどうしようもない、そんな叫びがほとばしっている。不良の装いをしているのではなく、不良そのものなのだ。わたしはそこに魅了されたのだろう。ある意味潔く、ある意味で手に負えない、どうしようもない人生。
中也の作品は高校の教科書に掲載されるなどして、最低でも一度は触れたことがある人も多いだろう。
そして多少日本近代文学に触れた人なら、本書表紙のあのあまりにも有名な写真を必ず目にしているだろう。
山高帽をかぶった童顔の、目だけが異様にキラキラと輝いている……まさしく詩人然として中也のポートレートから、一体誰があの人生を想像できるだろうか?
医業の家に生まれながら学業では不登校・中退を繰り返し、女と同棲するも破局や略奪愛を繰り返す。終生まともに働いたことはなく、最後の最後まで実家からの資金援助で生活していた。童顔に似合わず気性が荒く、特に酒が入ると必ずひとに絡み手が付けられないほど暴れる。結婚し子どもが生まれると一転子煩悩な父となり、溺愛の日々を送るも夭折の後には精神を病んでしまう。そして結核性脳膜炎を患い30歳という若さで亡くなるのだが、ほぼ憤死のようなものだ。
しかも死の間際、最後の最後まで迷惑をかけ続けた母親に「僕は孝行者だったんですよ」と言ったという。正直どの口が言っていると思われるだろうが、それに続く「今に分かるときが来ますよ」という言葉通り、彼の作品はその名声とともに今でも読み継がれている。
本書は中也がその折々で語った言葉の一文を紹介し、その言葉にまつわるエピソードを簡潔に添える体裁をとっている。
それぞれのエピソードを知る人であればその背景なども相俟って容易に言葉の意味を理解できるかもしれないが、果たして何も知らない読者がそれに触れたらどうだろうか?
本書は、短い言葉とエピソードを頼りに詩人・中原中也がその時なにを思い何を感じていたのかを想像させてくれるう。彼の言葉そのものを材料にその心象風景に触れる、まさしく"中原中也"という「詩」を読む本だ。
以前、別の文豪名言シリーズの太宰治本で「ナイフを持つ前に太宰を読め」という副題がついていた。
太宰はじめ無頼派の作家の語る言葉はとにかく切れる。読む側の心にスッと入り込んで一気に切り裂いていく、そんな凄まじい切れ味の刃物そのものだ。
一方で中也はどうか? 無頼派が鋭利な刃物なら、中也は刃がつぶれ刃こぼれもしている刃物――もはや鈍器だと思う。斬りつけるのではなく、叩き切る。むしろ叩き潰してくる。
ではなぜそんなに刃がボロボロなのかといえば、それはすでに中也が自身を散々に切り刻んだからに他ならない。
中也は太宰を「青鯖が空に浮かんだような顔をした」ヤツと称し、ことあるごとに喧嘩を吹っかけていたらしい。太宰は「とてもやりきれる相手じゃない」と辟易するばかりだったという。
そんな太宰は中也の死の知らせを受けた晩、舎弟のように付き従えていた檀一雄と酒を酌み交わしこう言ったといわれる。
「中原は死んでも中原だね……」
Amazon
さよならを言うまえに