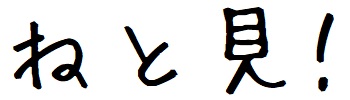阿部 謹也 訳
出版社:岩波書店(岩波文庫 赤455-1)
発売日:1990/05/16
中世ドイツの奇人による糞尿譚。下品極まりない逸話の中に垣間見える中世ヨーロッパの賤民世界と、上流階級への痛切なるアイロニー。
日本ではあまり馴染みのない名前かもしれないが、ヨーロッパ、特にドイツ周辺国では幼少時から絵本などを通じ、文字通り子供から大人まで知っているティル・オイレンシュピーゲル。日本の"吉四六"などと比されたりするが、ティル自身はかなり強烈ないたずら好き、スカトロ趣向の持ち主なので、吉四六とは似て非なるものくらいの感覚で受け取っていた方がよいかもしれない。
さてこのティル・オイレンシュピーゲルだが、その実際は一般社会の外側を生きる放浪者、中世ヨーロッパにおけるいわゆる賤民。その彼が上位階級たる貴族や聖職者はじめ、裕福な商人、果ては一般の庶民までを相手に繰り広げるいたずらは、社会からつま弾きにされた者が既存の階級社会を風刺する以上に痛切な皮肉と断罪の証といえる。なぜなら、その"いたずら"の度があまりにすぎているからだ。人を傷つけるのはもちろん、幼児なら大喜びしそうな排泄物や下品な言動が繰るページ繰るページこれでもかと繰り返されている。現代的視点からするとそのハメの外し方は常軌を逸している感があるが、グリム童話然り、中世ヨーロッパの物語の中に宿る残忍・残虐性を考えるなら、これもまたうなずけるかもしれない。
そうした汚らしい逸話が続く本書だが、じっくりと熟読しようとしてみると、実はこれがかなり手ごわかったりする。
前記の通り主人公・ティルはいわゆる賤民であり、その"いたずら"の矛先が向かうのは彼をつま弾きにした"社会"だ。そうした当時の社会的な背景はもちろんのこと、市井の暮らしや文化的な側面にもかなり深い造形がないと読み解けない部分も多い。また、ドイツ語方言による言い回しのすれ違いや韻の踏み方、ダブル・ミーニングの頻出など、それこそドイツ中世史を紐解こうとするほどの基礎知識が必要となる。
裏を返せば『ハーメルンの笛吹き男』などにもいえるが、当時の社会的な空気感をつかみ取るには絶好の資料だともいえる。
 ハーメルンの笛吹き男 伝説とその世界 |
 中世賤民の宇宙 ヨーロッパ原点への旅 |
そんな本書を題材に、19世紀末、R・シュトラウスによって作曲されたのが『交響詩 ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』だ。
吹奏楽などでもコンクールの自由曲として選ばれることの多いこの曲だが、原作に比して大分毒気が抜かれて洗練されたような雰囲気漂う名曲となっている(シュトラウスの作品なのだから当然といえば当然だが)。
Amazon
カラヤン指揮 R.シュトラウス
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」
「むか~しむかしあるところに……」という昔話の冒頭を彷彿とさせる静かな始まり方の直後、ホルンのソロで主人公・ティルの自己紹介のようなパートが出てくるが、この部分が主題となって、全編をとおして繰り返しさまざまな形で出現してくる。
原作中のから4つの逸話が引かれ、それぞれに楽器の特色を生かした旋律や効果音が入るのだが、それらがティルの動機や登場人物たちの感情的な表現となっていてとてもユニーク。
しかしその中でも特筆すべきは、曲の最後でティルが処刑されるという場面。
原作では刑死とも病死ともされていてはっきりとはしていないものの、R・シュトラウスの本曲では明確に刑死とされている。曲調もそれまでの楽しく軽やかなイメージから、突然重々しく混沌とした空気に変わる。
結局曲の終盤で刑死によって命を落としたティルなのだが、その後でも彼のいたずらは続く。これは原作でもまた同じだ。
彼の亡骸を収めた棺は、図らずも墓穴の中に垂直落下してしまう。するとそこにいた人々は
「そのままにしておこう。彼の一生が変わっていたように、死体も変わった姿を望んでいるんでしょう」(阿部謹也 訳≪岩波文庫 赤455-1≫)
とそのまま土をかけて埋めてしまった。
そこでその墓碑銘には『ここにオイレンシュピーゲル"立つ"』と刻まれたというオチがついている。
なんとも人を小バカにしたような作品だが、そこに込められたアイロニーやユーモア、風刺というものは、現代社会を生きる私たちにも今なお多くのことを語り掛けてくれていると思う。
Amazon
日本楽譜出版社 NO.282 リヒャルト・シュトラウス
ティルオイレンシュピーゲルの愉快な悪戯