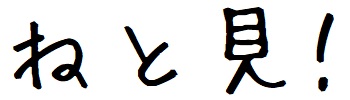先祖の話
柳田國男
出版社:角川学芸出版(角川ソフィア文庫)
発売日:2013/06/21
柳田國男が未来に託した遺書
太平洋戦争末期、アメリカ軍による本土空襲が激化した昭和20年4月から5月にかけて一気に書き上げられたという本書は、柳田國男の傑作のひとつといわれている。明日どうなるかも分からない状況下において、どうしても「書いておかねばならない」と綴られた日本の先祖観と祖霊信仰についての81の短文が収められている。では一体なにが著者をそこまで駆り立てたのだろうか?
もちろん戦況激化のさなか、疎開することなく日々空襲の砲火に戦々恐々としている老体を振り返った部分もあるだろうが、なによりもその中心にあったのは、若くして戦火に散った者たちは誰に祀られるのか、またその祀られるはずの「家」自体が崩壊してしまうのではないのかという危惧だった。明治以降、国や地方が管理する「晴の祭場」すなわち護国神社などの制度化された神社に戦死者が英霊として祀られていたが、果たしてそれが最適解なのか、著者は疑問視していたのである。むしろ、古より日本人の生活の中に根付いてきた先祖観や祖霊信仰に基づいて祀られるべきではないか? そうした思いから、日本人の風習や霊魂・死生観を通してその根底に潜む精神性を明らかにしようとしたのが本書である。
冒頭で本書は著者の傑作のひとつと紹介したが、同時に問題の多い作品であることは刊行当初から指摘されており、今なお賛否両論絶えない。実際著者の弟子の一人である有賀喜左衛門は「彼(柳田)の傑作の一つだがまた問題の多い作」としたうえで「それだけに興味はつきない」と指摘している(有賀喜左衛門『一つの日本文化論』)。いずれにしても、著者が未来の日本社会に残したかった精神性や社会の在り方への考察、すなわち先祖との目に見えない繋がりや共生していこうとする人々との繋がり、そうした精神性や関係性を大切にしようという指摘は現代日本にあってこそ忘れてはならない点である思う。
本書は81の短文より構成されていると書いたが、内容は難解だがどの項目もほんの数ページで読みやすいので繰り返し読み込むにはちょうど良い。本書が書かれた経緯を記した冒頭の「自序」も圧巻だ。